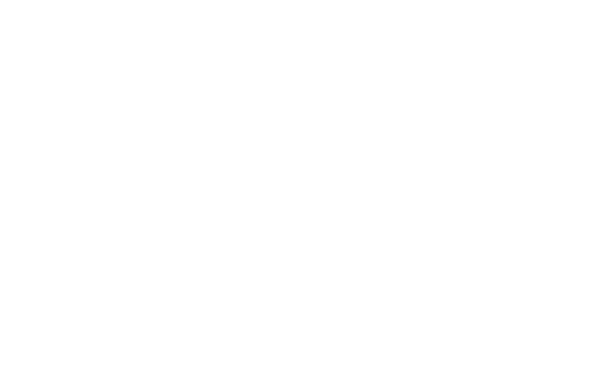2024年01月31日
サブスクのまだ未確定な将来債権でファイナンスできるのは、革新的 | 家具と家電のレンタル・サブスク「CLAS」がRBFを選んだ理由
株式会社クラス
戦略財務本部 本部長 | 原 巧 氏
循環型の家具と家電のレンタル・サブスク「CLAS(クラス)」を運営する株式会社クラス(以下「クラス」)。モノを扱うビジネスの性質上、その資金調達手法はベンチャーキャピタル(以下「VC」)からの資金調達、融資、リース、セールアンドリースバック、トランザクションファイナンスや債権流動化と多岐に渡ります。
そんなクラスは2024年1月、総額19.4億円の資金調達を発表しました。この中には、Yoii Fuelを通したレベニュー・ベースド・ファイナンシング(以下「RBF」)で調達した資金も含まれています。
数々の手法を利用して大型資金調達を実施したクラス社において、RBFまたはYoii Fuelはどのように映ったのでしょうか。サブスクビジネスにおけるRBFの位置づけやYoii Fuelの使い後について、クラスでファイナンス全般を主管する、原巧さんに聞きました。
▶Yoii Fuel 資金調達シミュレーター:RBFによる資金調達額を1分でシミュレーションする
※以下、主に会社を表す場合は「クラス」、サービスを表す場合は「CLAS」と表記します。

原 巧 | HARA Takumi
株式会社クラス 戦略財務本部 本部長
慶應義塾大学卒業後、London School of Economics (LSE)社会学部修士課程に留学。在学中に外資系投資銀行の香港支店及び東京支店にて投資銀行部門の長期インターンを経験。帰国後は新卒で投資ファンドに入社。その後、外資系コンサル、事業会社(スタートアップ含む)にてCFO、社長室長等を歴任。2022年よりクラスに参画し、戦略財務本部ゼネラルマネージャーに就任。
家具と家電のサブスク。身軽さを望む個人や法人の利用が増加
── まずは原さんの経歴を教えてください。
私は学生時代に外資系の投資銀行でインターンをして、そこでファイナンスに興味をもちました。その後、新卒で投資ファンドに入社し、投資やM&Aに従事しました。その後、外コンを挟み、事業会社やスタートアップで社長室長やCFOを経験しております。2022年からクラスの戦略財務本部 本部長を務め、CFOと名乗ってはいませんが、ファイナンス関連はすべて私の担当です。
── クラスに参画したきっかけを教えてください。
モノを扱うサービスであるCLASは、それに伴って会計やファイナンスの複雑性も高くなるので、正直に言って最初はあまり気乗りしていなかったんです。ただ代表の久保に会って話を聞いてみると、事業の解像度が非常に高く、未来を見据えて話す姿が印象に残りました。この人とだったらIPOやその後の成長も実現できる。そう思ってクラスに入社しています。

── それでは、CLASについて教えてください。
「CLAS」は、家具と家電のレンタル・サブスクサービスです。大きく個人向けの「CLAS」、法人向けの「CLAS BUSINESS」を用意していて、オフィス構築・大型オフィス家具のお試し利用と、デベロッパー・ハウスメーカー向けにモデルルーム、家具付き賃貸(マンスリーマンションなど)と、事業展開しています。2023年12月時点で個人向けに2,000点、法人向けに4,000点の商品を用意。月額制で1点から必要な期間だけ利用可能です。なお、商品の中にはCLASのオリジナルプライベートブランドである「CIRCLE」の家具も含まれています。
- 「CLAS」:https://clas.style/
- 「CLAS BUSINESS」:https://clas.style/biz/
- 「CLASホームステージング」:https://clas.style/biz/staging

── ユーザーにはどのような方が多いのでしょうか。
個人では25〜40歳の単身やDINKsの方々など、ライフステージが変化しやすい方を中心にご利用いただいています。近年は在宅勤務になったり、在宅と出社を組み合わせたハイブリッドワークになったりと、働き方や生活環境が変わりやすい時代。引っ越すたびに、ベッドやソファ、冷蔵庫や洗濯機といった大きな家具や家電を移動したり廃棄したりするのは大変ですよね。そもそもモノを所有したくないという方も増えていますし、そういった方々にCLASは広がっています。
法人向けは住宅領域では大手不動産デベロッパー、オフィス利用では循環型ビジネスに関連した上場ベンチャーの成長著しいスタートアップのご利用が多いですね。コロナ禍を機に環境変化に柔軟に対応できるようにしておきたいと考える会社が多くなっているようで、最近はそういった会社のご利用が増えています。
サステナブル実現の秘訣は「在庫管理システム」
── CLASはサステナブルにも貢献するサービスですね。
はい。特にこの2年ほど、サステナブルに関しては会社としてしっかり取り組んできました。自社独自の取り組みはもちろん、例えば環境省には令和4年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業(デジタル技術活用効果実証)」に採択され、レポートも公開しています。
※クラスは、環境省の令和4年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業(デジタル技術活用効果実証)」に2022年12月に採択され、2023年2月時点でCLASがサービス展開している家具を対象に試算した結果、従来の売り切り型ビジネスと比較し、CO2排出量36%削減、廃棄物発生量38%削減の効果が認められました。
詳細は下記のレポートをご参照ください。
クラスの事業活動における、脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果

(ベースライン:売り切り型、脱炭素型2Rビジネス:クラス事業)
出典:令和4年度デジタル技術を活用した脱炭素型2Rビジネス構築等促進に関する実証・検証委託業務 報告書
── 上図によると、例えばテーブルを買って何年か使い廃棄するよりも、CLASから借りたほうがCO2排出量は少なくなるとのことで、驚きました。
そうなんです。CLASと購入した場合とを比較すると、CO2が36%削減されます。端的に説明すると、家具のバリューチェーンの中で最もCO2が排出されるのは製造時で、CLASを使っていただければ売り切り型ビジネスよりも家具の寿命が伸びるので、家具を作る量が減り、結果としてCO2排出量が減るというわけです。もちろん製造時以外にも配送や保管にもCO2は排出されますが、それよりも削減効果の方が大きいという結果になっています。
── 家具の寿命を伸ばすCLAS独自の工夫を教えてください。
例えば、パーツ単位での在庫管理です。在庫管理としては「テーブル×1」ではなく「天板×1、脚×4......」と部品単位で管理・保管しています。部品にはQRコードを貼っていて、これが個別IDになっており個品管理しているんです。

なぜこんなことをしているのか。それは循環型のレンタル・サブスクというビジネスに起因しています。例えばソファを貸し出して戻ってきた際に、ソファの脚(部品)が壊れていたとしましょう。もし「ソファ×1」という形で在庫管理をしていたら、脚の部品情報がないので仕入れたり修理できず、このソファは廃棄するしかない可能性があります。しかしパーツ単位で管理していれば、その壊れた部分だけ替えて、またお客さまの元へ届ければいい。こういったことを実現するためです。
── 部品を交換すれば使えるはずなのに、これまでは管理の仕方のせいで廃棄するしかなかったわけですね。この取り組みは創業期からされていたのでしょうか。
はい、創業時からずっとこのやり方です。創業してから半年程度は、ずっとこのシステムの構築に時間を費やしていたと聞いています。

ショールーム(目黒区青葉台)では、CLASでレンタル可能なオフィス家具が体感できます
── 素晴らしいですね。ただ在庫管理の難易度は跳ね上がるのではないでしょうか。
ご指摘の通り、非常に大変です。ただこのシステムは、リペアからECサイトの裏側の管理画面まで、全て基幹システムに繋ぎ込まれていて、最低限の登録だけすれば、あとはシステムが自動で必要な情報を動かしてくれるようになっていて、運営には人の手がほとんどかかっていないんです。ロケーションを変更した時に登録するくらいですね。
他社ですと、何か登録作業が必要なときにCSVデータをダウンロードして別のシステムに登録しなおすといった作業が必要なことが多いと聞いていますが、CLASでは単にステータスを変えればいいだけです。このシステムは他社との差別化要素になっていると思います。
モノのサブスクが故のファイナンスの課題
── それではファイナンスのお話も聞かせてください。CLASのビジネスモデル上、ファイナンス面ではどういった特徴が出てきますか?
やはり「モノの『サブスク』」であることが、最大のポイントとなります。CLASのファイナンス上の特徴は、損益計算書(以下「PL」)とキャッシュ・フローの乖離が大きい点です。モノを仕入れた時点でキャッシュは一気に出ていきますが、PL上では減価償却費は期間配分される。つまり、キャッシュアウトフローがPLに反映されるのに時間がかかるので、実態としてはPLの見た目以上に資金が先に流出しているということです。
この乖離をどうやって外部の関係者に伝え、どうマネジメントするか。私がモノを扱うビジネスをしたことがなかったということもあって、最初はかなり思考錯誤しました。
また、同業他社の中にはファイナンス・リース(編注:購入に近いリース取引のこと)で商品を提供している会社も多いと認識しています。つまり売り切りに近いので、確定債権としてファクタリングなどの利用がしやすくなるはずです。一方CLASは「サブスク」であり、債権が確定しているとは言えません。そういった意味でサブスクのファイナンスは難しいですね。
▶RBF関連記事:銀行借入・ベンチャーデット・RBFの違いを実践的に比較する(デットファイナンス活用ガイド)
── これまで、資金調達手段としてはどのようなものを利用されてきましたか?
VCからの資金調達、融資、リース、セールアンドリースバック、トランザクションファイナンスや債権流動化、そしてYoii Fuelを通したRBFなどですね。
── 手法がたくさんあって大変そうです。
そうですね。モノがあるとやはりファイナンスの多様性は増え、難易度は上がります。でも担当者としては飽きないから楽しいですよ(笑)。
── 2024年1月に19.4億円の資金調達を発表されました。資金使途を簡単に教えてください。
主に商品仕入れ、人件費、基幹システム開発、物流費などです。運転資金は融資など、デット性資金を充てています。とはいえ、在庫投資に関してはリースを利用したりと、極力エクイティ性資金は使わないようにはしています。
── エクイティとデットのポートフォリオ(バランス)についてはどのように考えているのでしょうか。
現在は、エクイティとデットが半分ずつのイメージです。ただその比率は、事業のステージによって大きく変わると考えています。

創業から数年は与信が低い傾向にあるので、主にエクイティ資金を頼って事業を運営をせざるを得ないケースが殆どです。ミドルステージにまでなってくると、収益が安定し事業のランウェイが見えるようになり、与信も高まる傾向にあります。ここまでくるとデット(リースなどの手法を含む)も比較的利用できるケースが増えてきます。今後レイターステージまで進んだ際には、資金調達のほとんどはエクイティに頼らず、デット性の資金で運営することもあり得ると考えています。
── エクイティとデットのポートフォリオや在庫投資の方針は、会社の成長が変えてきたのでしょうか、それとも原さんが変えてきたのでしょうか。
両方ですね。会社が成長して与信が上がってきたが故に融資が受けられるようになったという面もありますし、多様な資金調達手法は私のような専任の担当者が就くまで難しかったのも事実です。私がファイナンス専任になったからこそ、できることが増えた面はあると思います。

どの手法と比べても、手間が少ないのがYoii Fuel
── それではRBFについて聞かせてください。RBFの利用は、今回のYoii Fuelからの調達が初めてでしょうか。
Yoii Fuelが初めてでした。Yoii Fuelの話を聞く前からRBFの存在は知っていましたが、正直に言うと、最初はファクタリングみたいなものかと思っていたんです。でも使ってみたら「ファクタリングとは全然違うな」と考えを改めました。
例えば、ファクタリングは確定債権しか取り扱ってもらえないケースも少なくありません。一方でRBFは、サブスクのような必ずしも確定しているといえない将来債権でもファイナンスできるという点が非常に革新的だと感じています。
サブスクビジネスを運営するにあたっては、ファイナンスは運営の肝であり、CLASに限らず不安を抱える事業者は多いはずです。そういった不安やビジネスモデルに対応するスキームであるRBFは、サブスク事業者にとっては嬉しいですよね。

▶RBF関連記事:【調達前に確認】RBFのメリットと押さえたいポイント5つ
── Yoii Fuelの利用に際して、手続き面で不便はなかったでしょうか。
ありませんでした。ストレスフリーで申請できて、使いやすかったです。必要書類をウェブにアップロードしていったらあとは審査を待つだけ。銀行融資など伝統的な資金調達手法と比較すると、はるかに工数負担が少なく感じました。手続き自体には30分もかかっていないはずです。
── リースや確定債権売却といった手法と比較してはいかがでしょうか。
例えば確定債権売却はその性質上、一案件ごとに債権を売却しなくてはなりません。そうするとどうしても手間と時間がかかるので、そのための工数を確保するのが大変なんです。一方で、RBFは事業単位で将来発生しうる債権を包括的に評価してくれるため、そういう意味ではYoii Fuelははるかに少ない手間で済みました。
個人的には、債権流動化への関心は高いんです。ただいざ利用しようとすると、信託方式(編注:資産を信託してその受益権を投資家に譲渡する手法)かSPC方式(編注: 資産をSPCなどの法人に譲渡し、これを原資とする債券を発行する手法)かという論点があったり、口座管理や毎月の報告義務も大変で、どうしても腰が重くなってしまう。Yoii Fuelみたいに負担が軽いならさらに使いやすいんですけどね。

── Yoii Fuelはサブスクサービスを提供している他の事業者にもオススメできそうでしょうか。
はい。実は今回RBFを使ってみて「ちゃんとRBFを理解できていなかったな」と私も反省したんです。そういう意味で、もっとRBFの良さが広く伝わってほしいと感じています。サブスクでファイナンスを充てられる手法は限られてくるので、そういう意味でRBF、Yoii Fuelはサブスクビジネスには貴重な資金調達手段です。サブスクサービスを提供されている会社は、ぜひYoii Fuelを検討してみてください。
▶Yoii Fuel 資金調達シミュレーター:RBFによる資金調達額を1分でシミュレーションする
── 本日はありがとうございました。引き続きYoiiでもクラスを応援させてください。
その他の導入事例
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。