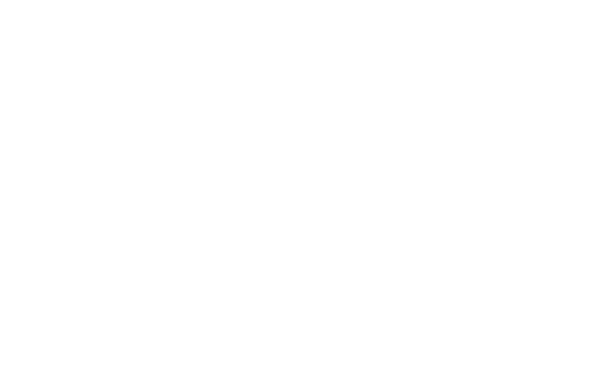2024年06月13日
政府によるスタートアップ向け資金支援策の概要
アーリーフェーズのスタートアップ経営者や、これからスタートアップとして起業することを考えている人にとって、政府や金融機関によるスタートアップの資金支援策について知り、それらを活用することは、事業を成長させていく上で大きな力になります。
今回の記事では、現在(※) 日本国内で行われているスタートアップ支援策について解説します。
※この記事は、2024年6月13日現在の情報に基づいて記載しています。
この記事のサマリ
- スタートアップが活用できる資金支援策は数多く存在し、税制優遇や公的金融機関のスタートアップ向け融資もその一つである
- 政府と各国立研究開発法人が連携して行う公募事業も多岐にわたり、大規模な補助金・助成金制度が備えられている
- スタートアップが社会課題の解決に担う役割は大きく、事業化までに長い時間や巨額の資金が必要な分野についても国家を挙げて積極的な支援が行なわれており、新規参入障壁を下げるための取り組みがなされている
スタートアップ向けの資金支援策
現在、スタートアップが活用できる資金支援策は数多く存在し、規模や対象フェーズも多岐に渡ります。本記事では、アーリーフェーズのスタートアップが活用できるものに絞って、大まかに分類した上で解説します。
税制改正(優遇税制)
政府は、スタートアップ企業を経済成長のドライバー、また雇用創出や社会課題の解決にも大きな役割を担うものと認識しており、起業や事業促進のために様々な支援策を打ち出しています。そのうちの一つが「税制改正」です。とりわけ、2024年4月に施行されたスタートアップ関連の税制改正により、今後ますますスタートアップに関わる資金の流れが活性化することが期待されています。
以下に、昨今改正が行われた代表的な優遇税制の例を紹介します。
エンジェル税制
まだリスクも大きい創業初期のスタートアップへの投資に重要な役割を担うと期待されているのが「エンジェル投資家」と呼ばれる個人投資家です。日本では、エンジェル投資を促進するための「エンジェル税制」という制度が設けられています。具体的には、個人投資家が投資を行った年の所得税を算定する際に以下のいずれかを選択し、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
- 投資額より2000円少ない金額を総所得から控除(投資対象は設立5年未満の企業、控除金額に上限あり)
- 投資額全額を株式譲渡益から控除(投資対象は設立10年未満の企業、控除金額に上限なし)
スタートアップ企業は、自社への投資がエンジェル税制の対象となるかを事前に確認することができます(事前確認制度)。これにより当該企業は投資家に対してエンジェル税制適用企業であることを説明でき、積極的な投資を検討してもらう一助になるでしょう。また事前確認が行われた場合には、経済産業省及び管轄する経済産業局のWEBサイトで会社名等を公表することができるため、さらなる投資の誘致やPRにも役立つと考えられます。
事前確認制度の申請は、各都道府県庁の窓口で行うことができます。
また実際に投資が行われた際には、当該投資についてエンジェル税制の適用を受けるため、改めて確認(株式の払込み等の確認)を受ける必要があります。
事前確認制度についての詳細は、下記の資料も参考にしてください。
なお経済産業省では近年の投資実態を踏まえ、エンジェル投資家から企業への直接投資以外にも、投資事業有限責任組合(ファンド)経由や、株式投資型クラウドファンディングの活用などによる株式取得もエンジェル税制の対象とするよう制度を拡充しており、その結果としてエンジェル投資家の数も近年飛躍的に増加しています。
エンジェル投資家の詳細については以下の記事も参考にしてください。
エンジェル投資家とは 〜概要・出会い方・出資を受けるにあたっての注意点の解説〜
オープンイノベーション促進税制
スタートアップ企業の出口戦略は多様化してきているものの、日本国内においてはIPOへの偏重が指摘されています。このような状況の中で、**事業会社によるスタートアップ企業のM&Aを促進すべく改正されたのが「オープンイノベーション促進税制」**です。
今回の税制改正では、発行済株式の取得によるM&Aも所得控除の対象とするように拡充されたため、スタートアップにとってはM&Aを受けやすくなりました。
※METI Journal:スタートアップを応援する税制改正。超重要ポイントを分かりやすく解説!より引用
スタートアップ企業にとっては、M&Aによって他社の傘下に入ることで、資金・人材・ネットワーク・ブランド力など、より大きな経営資源を活用でき、急速な成長のきっかけとすることができます。
また、M&Aによりスタートアップ企業を買収した事業会社がビジネスを継承することにより、起業家はキャッシュを得た上で経営から離れることも可能になります。その後、キャッシュを活用してエンジェル投資家や別のスタートアップを起業するシリアルアントレプレナーに転身することで、スタートアップエコシステムにおける人材・資金の循環を促進するという可能性もあります。
なお、オープンイノベーション促進税制が適用されるには、電子申請サービス「gBiz FORM」で申請を行う必要があり、M&Aを受けるスタートアップ企業側も「gBiz ID プライム」アカウントを取得する必要があります。
オープンイノベーション促進税制適用の詳細については、以下のWEBサイトも参考にしてください。
融資
一定の条件を満たすことで、スタートアップ企業にとって好条件で融資を行う公的機関や金融機関も存在します。以下に代表的な例を紹介します。
日本政策金融公庫の新規開業資金
日本政策金融公庫は政府系金融機関の代表的な存在で、地域の開業率を引き上げることで雇用機会を創出し、国内総生産(GDP)の引き上げを目指すべく運営されています。そのため、銀行などから融資を受けることが難しい、起業したばかりの会社や中小企業・小規模事業者への融資を積極的に行っています。
日本政策金融公庫では「新規開業資金」「資本性ローン」「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、起業・開業時に利用できる融資制度を提供しています。中でも起業・開業時に多く利用されているのが2024年4月より開始された「新規開業資金」です。
新規開業資金では、原則として無担保・無保証人で、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで融資を受けられます。 また自己資金要件も撤廃されており、自己資金を用意できなくても申し込みすることが可能です。さらに、2024年4月から一部の融資対象において、返済期間の延長や利率の引き下げなども行われています。
融資を希望する場合は、日本政策金融公庫に問い合わせるか、近くの商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、都道府県の生活衛生営業指導センターでも相談することができます。
日本政策金融公庫:新規開業資金より引用
信用保証協会の保証つき融資
信用保証協会(「保証協会」とも呼ばれる)は、中小企業・新規企業の健全な育成発展の役割を果たすため、「信用保証」をもって金融の円滑化を図る公的な保証機関です。 保証協会も日本政策金融公庫同様に公的な機関ではありますが、保証協会自体は融資を行わず、あくまで「保証」のみを行う点が異なっています。
金融機関を通じて審査を申し込むと、保証協会が会社の信用調査や審査を行い、審査に通った場合は金融機関に信用保証書を発行、金融機関は信用保証書に基づいて融資を行う、という流れになります。
保証協会が提供している制度としては「創業関連保証」「再挑戦支援保証」「スタートアップ創出促進保証制度」などが挙げられます。いずれも創業まもない、またはこれから創業するスタートアップが金融機関から融資を受けるのをサポートしてくれる制度です。
スタートアップのアーリーフェーズに活用できる融資の詳細については、以下の記事も参考にしてください。
補助金・助成金
創業期のスタートアップが活用できる各種の補助金・助成金も拡充されています。業種業界を問わず申請・応募できるものも存在しますが、この章では、社会課題の解決へのインパクトが大きいと考えられているものの、事業確立までに特に多額の資金がかかる特定分野のスタートアップを対象とした公募事業について紹介します。
ディープテック・スタートアップ支援事業
ディープテック・スタートアップ支援事業とは、2023年度から国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(略称:NEDO)により実施されている公募事業で、革新的な技術の事業化や事業成長の実現を目指す「ディープテック・スタートアップ」に対し、以下の3つのフェーズにおいて研究開発や事業化のための支援を行っています。
| フェーズ | 助成金の額 | 事業期間 | 事業形態 |
|---|---|---|---|
| STS フェーズ(実用化研究開発(前期)) | 3億円以内または5億円以内 */事業期間 | 1.5~2年程度(ただし同一フェーズ内で最長4年) | 助成(NEDO負担率 2/3以下) |
| PCA フェーズ(実用化研究開発(後期)) | 5億円以内または10億円以内 */事業期間 | 1.5~2年程度(ただし同一フェーズ内で最長4年) | 助成(NEDO負担率 2/3以下) |
| DMP フェーズ(量産化実証) | 25億円以内 */事業期間 | 1.5~2年程度(ただし同一フェーズ内で最長4年) | 助成(NEDO負担率 2/3または1/2以下) |
*事業会社連携や海外技術実証で上限引き上げあり。
応募に関しては事業がどのフェーズにあっても可能で(適合する1フェーズに対してのみ応募可能)、審査を通過した場合には、次回の資金調達実施までの期間(1.5〜2年が目安。最長で4年)に必要な事業運転資金が提供されます。
各フェーズでの事業実施後、ステージゲート審査で認められた場合には次のフェーズでも連続的に支援を受けることが可能になります(トータルで最大6年間・最大30億円の助成金額上限あり)。
※NEDO:「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業」及び「GX 分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業」に係る公募要領より引用
開始年度の2023年度には、46社のスタートアップ企業が当該事業の支援対象として採択されています。
ディープテック・スタートアップ支援事業の詳細については、以下のWEBサイトも参考にしてください。
NEDO:ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業
SBIR推進プログラム
SBIR推進プログラムは、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(略称:NEDO)により実施されている公募事業で、各省庁が提示する多様な社会課題の解決に貢献する研究開発の促進や、成果の円滑な社会実装を実現するスタートアップ企業等を支援することを目的としています。
SBIR推進プログラムでは、スタートアップ等の開発の段階に応じた支援を想定しており、以下の2つのフェーズにおいてそれぞれ公募・支援を実施しています。
- フェーズ1:概念実証(POC:Proof of concept)や実現可能性調査(FS:Feasibility study)の段階。
- フェーズ2:POCやFSを完了し、実用化に向けた研究開発の段階。
また経産省とNEDOが連携してフェーズ1・2とその後の支援を一気通貫で行う「一気通貫型」と、経産省以外の他の省庁が提示する課題やニーズに基づいて、経産省・NEDOがフェーズ1またはフェーズ1・2を実施し、ニーズ元省庁がその後の支援を行う「連結型」の2つの型が取られており、型とフェーズの組み合わせでそれぞれに事業期間や助成金の上限が異なります。
一気通貫型
| フェーズ | 助成金の額 | 事業期間 | 事業形態 |
|---|---|---|---|
| フェーズ1 | 2000万円以内 | 1年以内 | 定額助成(NEDO負担100%) |
| フェーズ2 | 1億円以内 | 2年以内 | 助成(NEDO負担率 2/3以下) |
連結型
| フェーズ | 助成金の額 | 事業期間 | 事業形態 |
|---|---|---|---|
| フェーズ1 | 1500万円以内 | 1年以内 | 定額助成(NEDO負担100%) |
| フェーズ2 | 実施機関による(NEDO実施の場合、5000万円以内) | 実施機関による(NEDO実施の場合、2年以内) | 実施機関による(NEDO実施の場合、助成率 2/3以下) |
※NEDO:SBIR推進プログラムより引用
現在、一気通貫型・連結型それぞれに公募実施中の研究開発課題が提示されています。
※NEDO:SBIR推進プログラムより引用
SBIR推進プログラムの詳細については、以下のWEBサイトも参考にしてください。
創薬ベンチャーエコシステム強化事業
創薬ベンチャーエコシステム強化事業は、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(略称:AMED)により実施されている公募事業です。
新薬の開発には多額の資金を要しますが、日本国内の創薬ベンチャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状となっています。このような状況を受け、政府の方針のもと感染症のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的でこの事業が創設されました。
本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、ハンズオンによる事業化サポートを行う創薬事業に特化したベンチャーキャピタル(VC)をAMEDが認定し、それらの認定VCによる出資を要件として、新薬の開発段階にあるスタートアップ企業に対してAMEDが補助金を交付し、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図っています。
「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」の事業スキーム
令和6年度の公募情報は以下のようになっています。
-
公募補助事業課題
1.感染症のワクチン・治療薬の開発のための革新的な技術開発
2.感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発のための革新的な技術開発
-
補助金の額:1課題当たり総額100億円まで(間接経費及び認定VC出資分含む)
※上限を超える提案も可能
※AMEDは補助対象経費の2/3を上限に補助金を交付
-
補助事業期間:最長で令和13年9月まで
※課題毎に設定
創薬ベンチャーエコシステム強化事業の詳細については、以下のWEBサイトも参考にしてください。
AMED:令和6年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」に係る公募(第5回)について
宇宙戦略基金
宇宙戦略基金とは、内閣府・総務省・文科省・経産省と国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(略称:JAXA)が連携して設置する、大学・民間企業などへの資金提供プログラムです。激化している国際的な宇宙開発競争に遅れることなく、日本の宇宙開発利用を加速するために必要な基金として設置されており、10年間で総額1兆円規模の支援が見込まれています。
初期投資が比較的少なくて済むIT(情報技術)分野などと比べ、宇宙分野は事業が軌道に乗るまでに長い時間と巨額の費用がかかる難しさがあります。
そういった宇宙分野の投資リスクを踏まえ、スタートアップ企業や大学研究機関が自己負担なしで技術開発に挑むことを可能にし、参入障壁を下げるべく、運用が動き始めています。
宇宙戦略基金の支援対象テーマとしては、下記の3つが挙げられています。
- 輸送:高頻度のロケット打ち上げに向け、再使用できる地上基盤づくり など
- 衛星等:安定して通信できる商業衛星コンステレーション(小型衛星群)の構築/3次元計測ができる光学衛星による観測システムの構築/強固なセキュリティーを実現する衛星量子暗号の通信技術開発 など
- 探査等:月面での運用を想定した再生型燃料電池の開発/有人活動での利用に対応する物資補給システムの構築 など
この事業においてJAXAは支援先の選定、進捗管理、専門的助言、目標管理など、多岐にわたる役割を担うことになります。
JAXAが資金配分機関として特にマネジメントを行うべきテーマかつ現時点では収益化が困難な技術開発については「委託」での支援、将来的に民間事業者による商業化等、実施者の利益も大きいと見込まれる技術開発テーマについては「補助」 での支援が行われます。
「宇宙戦略基金」の事業スキーム
※内閣府 宇宙開発戦略推進事務局:宇宙戦略基金について(全体概要)より引用
宇宙戦略基金については、補助金の明確な上限等は現在設定されておらず、委託・補助を受ける団体の規模や技術成熟度等により、必要経費に対する柔軟な支援が予定されています。
また、技術開発が進み事業化リスクが低下するにつれて段階的に補助率を低減させることにより、スタートアップ等の早期の自立化を促す仕組みになっています。
なお、支援機関の上限は最大10年の範囲内で、各技術開発テーマごとに定められます。
※内閣府 宇宙開発戦略推進事務局:宇宙戦略基金について(全体概要)より引用
*TRL…Technology Readiness Levelの略。NASAまたはDOE(アメリカ合衆国エネルギー省)が定めている基準を参照して判断する。
宇宙戦略基金の詳細については、下記の資料も参考にしてください。
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局:宇宙戦略基金について(全体概要)
今回は、スタートアップ向けに現在制度化されている政府の資金支援策についてまとめました。日本国内でもスタートアップ育成の機運はますます高まっており、今後も多様な形での支援策が登場することが期待されます。
上記で紹介した公的な支援制度のほか、最近では新たにRBFという資金調達手法も注目を集めています。簡単に説明すると、過去の売上データから将来の売上を予測し、将来の売上の一部を利用して資金調達するという手法です。事業を開始し、売上が立つなど成長してきたタイミングであれば活用することが可能です。
RBFについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
5分でわかる「レベニュー・ベースド・ファイナンシング(RBF)」デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段
※免責事項
当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。
デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。
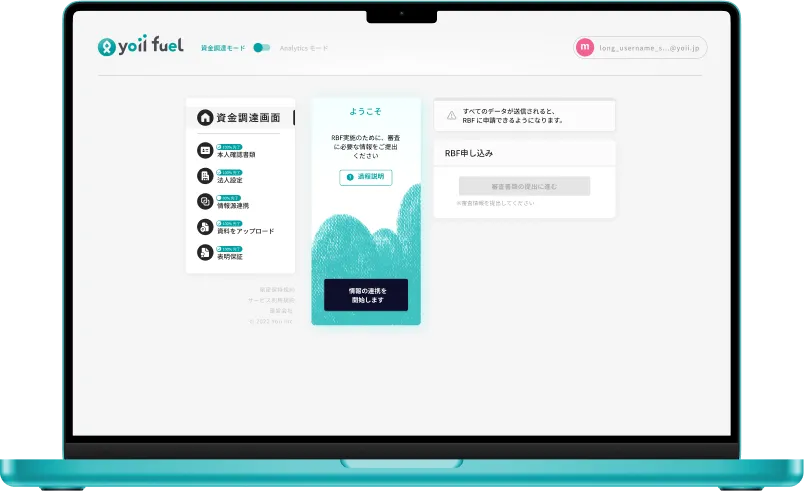
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
その他の記事
RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。