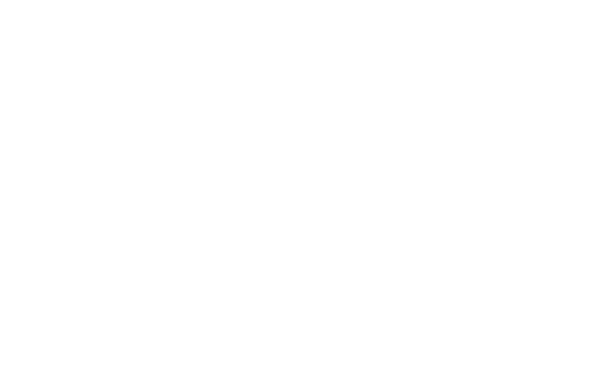2025年09月26日
新株予約権(ストックオプション)のメリットとデメリットを解説!成功・失敗事例、他の資金調達手段との比較もあわせて紹介
新株予約権とは?基礎から理解する
新株予約権の基本的な仕組みと種類
発行の流れと投資家・株主への影響
新株予約権のメリット
資金調達手段としての強み
社員へのインセンティブや人材確保
株価上昇による投資家との関係強化
新株予約権のデメリットとリスク
希薄化による既存株主の価値の減少
会計処理・税制上の複雑さ
投資家・市場からのネガティブな評価
事例から学ぶ新株予約権の実際
成功事例
失敗事例
新株予約権と他の選択肢との比較
株式発行と比較した場合
従業員報酬制度と比較した場合
RBF(レベニューベースドファイナンシング)による資金調達と比較した場合
まとめ
参考資料
新株予約権は、資金調達と従業員のインセンティブを改善できる魅力的な取り組みです。一方で、株式価値の希薄化や会計・税務の負担など、注意点も抱える制度です。
この記事では、新株予約権の基本の仕組みからメリット・デメリットを詳しく解説します。記事を読み進めることで、以下の3つのポイントを掴めます。
- 企業側のメリットとデメリットを理解する
- 自社のフェーズに合う制度設計を考えられる
- 他の資金調達手段との使い分けを見極める
新株予約権とは?基礎から理解する
新株予約権は「将来の一定条件で株式を取得できる権利」であり、資金調達や従業員インセンティブに幅広く活用されています。ここでは基礎知識を整理し、全体像を掴みましょう。
- 新株予約権の基本的な仕組みと種類
- 発行の流れと投資家・株主への影響
新株予約権の基本的な仕組みと種類
新株予約権とは、あらかじめ決められた 行使価格 と 期間 に基づいて、新たな株式を取得できる権利のことです。株式をすぐに発行するわけではなく、「ある条件を満たせば、将来に株式を得られる」点が特徴です。
新株予約権にはさまざまな種類があります。大きく見ると、
「誰に対して発行するのか」
「有償か無償か」
「条件の公平性」
という3つの観点で以下のとおり分類できます。
発行対象による分類
- ストックオプション
社内の役員や従業員に権利を与える。企業価値を向上させるインセンティブとして活用できる。 - 社外向け発行
社外の投資家や金融機関などに権利を付与する。資金調達の手段として主に利用される。
割当方法による分類
- 無償割当
株主や従業員に対して無料で予約権を割り当てる。参加しやすい制度を設計できる。 - 有償割当
投資家や従業員などが一定の対価を払って予約できる権利を取得する。資金を調達する効果が高い。
発行条件による分類
- 公正発行
既存の株主全員に同じ条件で権利を与える。透明性と公平性を確保できる。 - 有利発行
特定の株主や投資家に有利な条件で発行する。資金調達や関係の強化に有効である。
新株予約権は「どの立場の人に、どんな条件で権利を与えるか」によって性格が変わる制度です。経営者や財務担当者は、自社の成長フェーズや資金調達の目的に合わせて、望ましい発行方法を選ぶことが重要です。
発行の流れと投資家・株主への影響
ここでは、新株予約権を発行するための流れを順に説明しましょう。発行によって投資家や株主に与える影響についても解説します。
新株予約権を発行するための手順としては、まず株主総会・取締役会での決議から始まります。この際に行使価格・期間などの募集事項が定められ、対象者に権利が割り当てられます。権利を持つ者は、条件を満たしたときに行使を申請すれば、新たな株式が発行される仕組みです。
投資家や株主への影響として重要なのが 希薄化リスク です。特定の第三者が新株予約権を行使すると株式数が増え、既存株主の持株比率が下がります。そのため、一時的に株価が下落する可能性があります。
一方で、投資家は
「行使価格は適切か」
「将来の成長と結びついているか」
を重視します。条件に納得できれば、中長期的に企業価値の向上につながると評価するケースも多いのです。
新株予約権のメリット
ここでは以下にあげる3つの視点で、経営者・財務担当から見た、新株予約権を発行するメリットを整理しましょう。
- 資金調達手段としての強み
- 人材確保・社員インセンティブの効果
- 株価上昇による投資家との関係強化
資金調達手段としての強み
新株予約権の大きな魅力は、資金調達の柔軟性にあります。 銀行からの借入に依存せず、将来の資金調達を確保できる点 が強みです。
発行時に有償割当とすれば、すくに資金を得られますし、権利行使時にも追加の資金流入が見込めます。銀行融資のように担保や保証人を必要としないため、スタートアップにとって利用しやすい制度です。
通常の株式発行とは異なり、新株予約権を利用すると、実際の株式数は権利が行使された時点で増えます。そのため、将来に備えた資金調達の仕組みとして機能します。
新株予約権付融資(ローン)を活用したケースでは、企業が短期的な資金繰りを安定させつつ、中長期の成長に向けた原資を確保できた事例もあります。
新株予約権付融資(ローン)とは、金融機関と融資契約を結ぶのと同時に、新株予約権を発行する仕組みです。将来的に株式価値が高まった際に、融資元もその恩恵を受けられます。金融機関のリスクが小さくなるため、通常のスタートアップ向け融資よりも積極的に導入されやすい傾向があります。
社員へのインセンティブや人材確保
新株予約権は 従業員に「会社が成長すれば自身の利益に直結する」という、働くためのモチベーションを与える強力な制度 です。
業績連動で支払う給与とは異なり、会社がすぐにキャッシュを出す必要はありません。成長段階の企業にとっては、直近の資金繰りによる負担が軽くなる、魅力的な制度です。
一方で社員にとっては、自社の株価が上昇すれば、権利を行使することで大きな利益を得られます。「会社と一緒に成長する」という意識を持ちやすくなり、熱意を持って働くインセンティブにつながる仕組みです。
海外のスタートアップではストックオプション制度が幅広く導入されており、優秀な人材の獲得と定着に大きな効果を発揮しています。日本でもIPOを目指す企業を中心に、役員や社員へのストックオプションが積極的に利用されるようになってきました。
またストックオプションは、優秀な人材を確保するための制度としても役に立ちます。報酬として年収にストックオプションを付ければ、実質的な待遇を引き上げることも可能です。
例えばある企業のCOO(最高執行責任者)からは、次のような声が上がっています。
「ストックオプションを使い、成果報酬比率を上げてくる人は、成果を出せる自信がある人なので、一流である可能性が高いと感じる。例えば、元の年収が約1.5億円の方を年収約5,000万円でストックオプションをつけて採用できたというケースもあった」
引用:経済産業省「令和5年度産業経済研究委託事業(スタートアップの成長のための調査)調査報告書(公表版)」
ストックオプションは、役員と従業員の間で、長期的な企業価値を共有する仕組みとして評価されています。
株価上昇による投資家との関係強化
新株予約権は、 株価の成長を見込む投資家との信頼関係を深める手段 にもなります。
投資家に新株予約権を付与すると、株価が上昇した際に大きなリターンを得られます。投資家は企業に対して、長期的な成長へコミットするように促せます。新株予約権は、企業と投資家が「将来の成功を分かち合う契約」として機能するのです。
例えば、業績と株価の目標値を達成した時のみ、追加的に資金を調達できる新株予約権を発行した事例があります。目標とした業績・株価の向上を実現しつつ、資金調達を通じて事業を拡大させ、投資家からの評価を高めました。企業側にとっても、投資家との関係を強化するとともに、より良い条件で資金を調達できるメリットもあります。
新株予約権のデメリットとリスク
新株予約権は資金調達や人材確保に役立つ一方で、 以下にあげるデメリットやリスクも 有しています。
- 希薄化による既存株主の価値の減少
- 会計処理・税制上の複雑さ
- 投資家・市場からのネガティブな評価
これらのデメリットやリスクを把握することで、新株予約権のメリットを最大限に引き出せます。
希薄化による既存株主の価値の減少
新株予約権が持つもっとも大きなリスクは、 既存株主の持株比率が下がってしまう「希薄化」 です。
新株予約権が実際に行使されると、発行済み株式の総数が増えます。そのため、既存株主の株式シェアが相対的に減ります。その結果、既存株主からすると魅力が薄れてしまい、短期的には株価に下落圧力がかかる場合もあるのです。
通常の株式発行による資金調達と比べると、新株予約権は行使までのタイムラグがあるため、将来の希薄化リスクが見えにくいです。新株予約権の発行に対して、株主が警戒感を示すケースもあります。国内でも、新株予約権の発行により、希薄化を強く懸念された結果、株主から反発を受けた事例がありました。
会計処理・税制上の複雑さ
新株予約権は 会計処理や税制の面で手間がかかり、導入後も継続的な対応が必要となります 。
まず、発行時には会計処理や監査上の検討が必要となります。権利の付与条件や公正価値の算定など、専門的な手続きを経なければならず、事務負担が大きくなります。
税制面では、社員にストックオプションを付与した場合の課税タイミングが問題になります。要件を満たした、無償発行のストックオプション(税制適格ストックオプション)を利用すれば、税制面では有利となります。権利を行使する時点で課税は生じず、株式を売却するまで税の支払いを繰り延べられるためです。
一方で、税制非適格のストックオプションでは、権利を行使する時点でも税が発生します。実際に株式を売却しなくとも税の支払いが生じるため、社員にとって大きなコストとなり得ます。
投資家・市場からのネガティブな評価
新株予約権は 条件設定次第で投資家や市場からマイナス評価を受ける可能性があります 。
例えば、発行数が多すぎたり行使価格が低すぎたりすると、株価が下落する場合があります。新株予約権の要件が適切でなく「既存株主の価値を犠牲にしている」とみなされ、希薄化に対する懸念が大きくなってしまうのが主な理由です。マーケットは、条件の妥当性をとても敏感に見極めます。
こうしたリスクを回避するには、発行の目的や条件を株主や投資家に丁寧に説明し、透明性を確保することが欠かせません。ネガティブな反応を防ぎ、むしろ成長戦略の一環として評価してもらえるように設計する必要があります。
事例から学ぶ新株予約権の実際
新株予約権は、設計と運用の仕方で成功する事例と失敗する場合に分かれます。ここでは成功・失敗した事例を通じて、新株予約権の実態を学びましょう。
成功事例
新株予約権をうまく活用した企業の共通点は、 資金調達と人材確保を両立させていること です。
新株予約権を通じて人材を確保できた事例として、メルカリの取り組みがあげられます。
メルカリは未上場の時期より従業員にストックオプションを付与し、上場時には35名が6億円以上の資産を獲得しました。採用時には行使価格や税制面を含め具体的に説明しています。社員に当事者意識を醸成させ、優秀な人材を確保できた事例です。
じげんは2016年に、業績要件型の新株予約権を発行し、投資家の間で話題になりました。この新株予約権は、営業利益率やその成長率、ROE、そして株価について到達目標を定め、これらを達成したら新株を発行できる仕組みです。
その後、2018年3月期の決算説明会で、目標は一部達成されたと報告されています。経営陣の業績向上に対するコミットメントを明確に示すことで、資金調達と市場での高評価を同時に目指した興味深い事例です。
海外のスタートアップでは、優秀な人材の採用・雇用維持を目的としてストックオプションが活用されています。日本でも同様の事例が増えており、この記事でも紹介したとおり、給与では競えない待遇を補うことが可能です。
失敗事例
新株予約権の失敗事例は、 希薄化リスクを軽視した設計や、説明不足による投資家からの信頼低下 が原因となるケースが多いです。
株式による資金調達を研究している学術論文においても、新たなファイナンスの手段により「大幅な株価下落が生じ、投資家・株主の不信感を強めるような事例」が報告されています。要件設定のバランスを欠いたことが失敗の要因と考えられます。
ストックオプションの発行にも注意が必要です。社員への説明が充分でなかった企業では、
「なぜこの権利がメリットになるのか分からない」
「思ったより所得が増えなかった」
などの理由で不信感を抱かれ、インセンティブの形成につながらないケースもあります。
ストックオプションが税制適格となる要件を満たしているかも注意しましょう。税制適格と認められないと、権利行使により取得した株式は給与所得とみなされ、高率の所得税を課される場合があります。税制の要件を充分把握していなかったために、ストックオプションを発行した従業員に高額の所得税が発生し、充分な報酬を渡せなかった事例もあります。
※個別の案件における税務処理の方法については、必ず専門家(税理士など)にご相談ください。
新株予約権と他の選択肢との比較
経営者や財務担当者が新株予約権を発行するか考える上では、他の資金調達方法と比べることで、自社に最適な選択肢を判断できるものです。
ここでは新株予約権と以下にあげる3つの選択肢を比較します。それぞれの資金調達手段の特徴を整理しましょう。
- 株式発行と比較した場合
- 従業員報酬制度と比較した場合
- RBF(レベニューベースドファイナンシング)による資金調達と比較した場合
株式発行と比較した場合
株式発行は 即時に資金を得られる反面、希薄化もすぐに起こる 点が特徴です。一方、新株予約権は 資金調達が将来に分散される 仕組みで、実際の希薄化は権利行使時まで発生しません。
株式発行は短期的な資金を確保するために適しています。しかし希薄化も急激に起きるため、市場の反応に注意が必要です。
新株予約権は将来の成長を見込んで、少しずつ資金調達を進めていくための制度と言えます。ただし権利を行使されないと、計画通りに資金調達ができなくなり、不確実性を含むファイナンス手段でもあります。
新株予約権を発行する前に、資金繰りの緊急度や株主構成への影響を比較・検討することが欠かせません。
従業員報酬制度と比較した場合
新株予約権は、 キャッシュアウトを伴わずに事業に対する意欲を高められる点 で、業績連動給などの従業員に対する報酬制度とは異なります。
業績連動給は成果が出ればすぐに現金で還元する必要があるため、従業員にとっては短期的な満足度が高いと考えられます。一方で、企業にとっては資金の負担が直ちに発生します。
新株予約権は株価上昇という中長期的な成果と、従業員の報酬が連動します。社員が「会社の成長に参加している」という意識を持ちやすい仕組みです。
どちらの制度を選ぶべきかは、企業のフェーズによって変わります。スタートアップであれば、資金を温存するために、ストックオプションはより魅力的な選択肢です。すでに基盤となる収益を持つ企業ならば、現金による報酬制度が適切になってくるでしょう。
RBF(レベニューベースドファイナンシング)による資金調達と比較した場合
RBF(レベニューベースドファイナンシング)とは、将来の売上予測に応じて、毎月の支払い額が決まる新たな資金調達方法です。 RBFで資金を調達したら、その後は一定の手数料を売上から分配し支払うことになります。
新株予約権とは性質が異なるため、制度の使い分けを検討するのがおすすめです。
新株予約権は資金調達によって希薄化リスクを伴います。発行条件や将来の株価次第で投資家による評価が変わるため、資金調達額の見通しが難しい側面もあります。RBFであれば、株式の希薄化リスクがないため、既存株主の価値を守りつつ資金調達できる点が強みです。また、調達できる金額も不確実性がなく、迅速に資金を受け取れます。
ただし、RBFは売上規模や収益モデルが明確な企業に適しており、成長初期で売上が安定していないと導入が難しい場合もあります。専門家と相談しながら、自社のフェーズに応じて新株予約権とRBFを使い分けることが重要です。
まとめ
新株予約権は資金調達や人材確保、投資家との関係強化を同時に実現できる魅力的な選択肢です。一方で、株式の希薄化や、税務・会計上の負担といったリスクもあり、念入りな準備が必要です 。
新株予約権によって資金調達するか検討する際には、他の調達方法との比較が重要です。改めて、ポイントをまとめておきましょう。
株式発行か?新株予約権か?
資金を短期的に調達するなら株式発行、将来を見越して資金を確保するなら新株予約権。
社員への報酬制度か?株式連動型か?
キャッシュを温存しつつ、中長期のインセンティブを与えたいなら新株予約権。
RBFなど他の資金調達方法との比較は?
既存株主の価値を守りたい、調達する金額が決まっているならRBF、株価の成長と一体で資金調達したいなら新株予約権。
成功・失敗の事例から分かるように、制度そのものよりも設計と運用の工夫が結果を大きく左右します。自社の成長フェーズや人材戦略、投資家との関係性を踏まえて、望ましい制度を選びましょう。
参考資料
株式会社じげん「「株価・トリプル25」達成条件型新株予約権の発行に関するお知らせ」
株式会社メルカリ「当社従業員並びに当社子会社の役員及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)付与制度の導入、及び、ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」
経済産業省「令和5年度産業経済研究委託事業(スタートアップの成長のための調査)調査報告書(公表版)」
松尾順介・大杉謙一・岡村秀夫(2008)「新しいファイナンスをめぐる問題について―MSCBおよび新株予約権をめぐって―」証券経済研究、第64号。
※免責事項
当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。
デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。
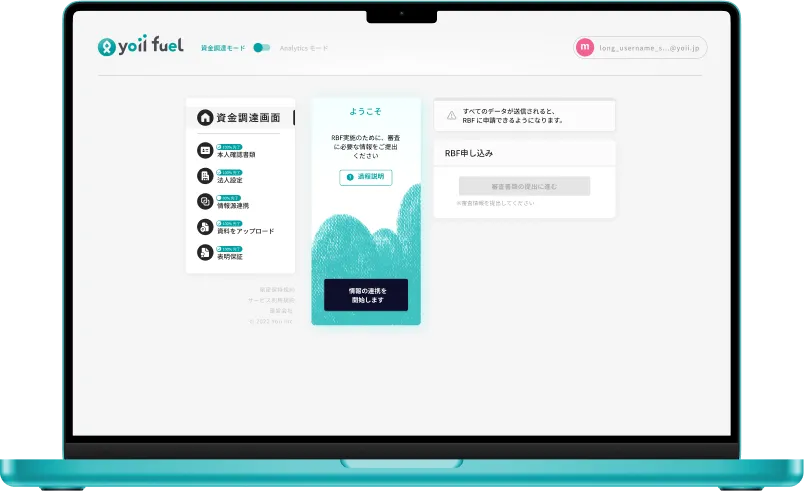
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
その他の記事
RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。