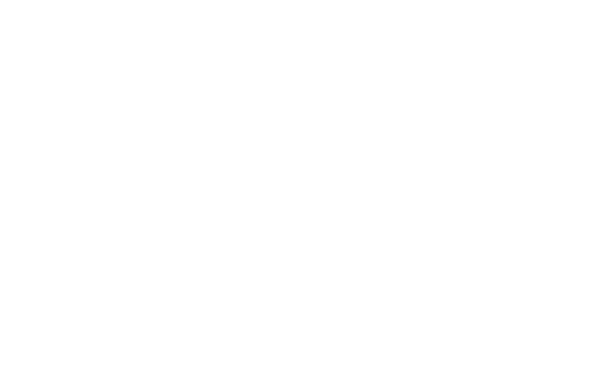2025年11月14日
今こそ知りたい銀行融資の基本 コロナ後の融資環境の変化や審査に通るためのポイントも解説
銀行融資とは?押さえておきたい融資の基本
銀行融資の仕組みと役割
銀行融資の主な種類と特徴
銀行融資のメリット・デメリット
コロナ禍以降の銀行融資の現状と今後の見通し
「ゼロゼロ融資」終了後の融資環境
利上げが進むことで銀行融資に与える影響
金融機関の姿勢と審査基準の変化
銀行融資に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 銀行はいくらまで貸してくれますか?
Q2. 担保や保証人がなくても借りられる?
Q3. 銀行融資の利子はいくらですか?
Q4. 融資の審査はどのくらいかかりますか?
Q5. 融資に通らない理由は何ですか?
まとめ
参考記事
銀行融資は中小企業やスタートアップにとって、堅実で歴史のある資金調達手段です。きちんと仕組みを理解し準備をすれば、十分に活用できる制度です。
しかし、創業間もない企業や銀行取引の経験が少ない経営者にとっては、わからないことばかりで不安を感じるのも当然でしょう。融資の種類や審査基準など、頭を悩ませるポイントも多いです。
新型コロナウイルス感染症が猛威をふるった頃は、たくさんの企業が融資を活用して危機を乗り越えました。新型コロナが落ち着いてきたのに伴い、融資をめぐる状況も変わりつつあります。
この記事では、銀行融資の基本的な仕組みから、コロナ禍以降の融資環境の変化、さらには審査に通りやすくするための具体的なポイントまで、幅広く解説します。
銀行融資とは?押さえておきたい融資の基本
銀行融資について理解を深めるために、まずは基本的な仕組みと種類、メリット・デメリットを見ていきましょう。
銀行融資の仕組みと役割
銀行融資とは、銀行が預金者から集めた資金を、資金を必要とする企業や個人に貸し出す仕組みです。
銀行融資は経済活動を支える重要な役割を担っています。この仕組みにより、企業は設備投資や運転資金を確保でき、事業をより大きく、素早く成長できます。
銀行が融資判断を行う際には、2つの目的を持って審査を実施します。
- 貸し出した資金が返済され、利息収入を確保できるか
- 返済が滞るリスクを最小限に抑えられるか
上で述べた目的を達成できるか、銀行は企業の財務状況や事業計画、経営者の資質などを総合的に評価します。審査結果をもとに、融資するか否か、融資する場合はその条件を決定します。
企業にとって銀行融資は、基本的な資金調達の一つとして位置づけられます。株式発行とは異なり、経営権を維持したまま必要な資金を確保できる点が大きな特徴です。
▶︎関連記事:スタートアップや中小企業が、銀行融資を活用するためのポイント・注意点を知りたい方は、以下の記事をお読みください。より実践的な知識が得られます!
「中小企業が銀行融資を活用できる実践ガイド:融資額の目安からステージごとの活用方法まで詳しく解説!」
銀行融資の主な種類と特徴
銀行融資にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や適した利用場面が異なります。融資を受ける際には、自社の状況や調達目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。
主な融資の種類
銀行融資は、大きく分けて以下の3つの種類に分類されます。
| 銀行融資の種類 | 特徴 |
|---|---|
| プロパー融資 | 銀行が独自の判断で直接貸し出す。融資限度額が高く、金利も比較的低め。審査基準は厳しい。 |
| 保証協会付き融資 | 信用保証協会が保証人となる。審査がプロパー融資よりやさしく、スタートアップ・中小企業でも使いやすい。保証料が必要で、審査に時間がかかりがち。 |
| 制度融資 | 地方自治体・政府系金融機関と信用保証協会が融資に協力。金利優遇や保証料補助のメリットあり。 |
▶︎関連記事:銀行融資を受ける際に、どの種類を使えばよいかお悩みの方はこちらの記事もご覧ください!
調達目的による分類
銀行融資を受ける際は、資金を調達する目的をはっきりさせておくことも重要です。目的を大きく分けると、設備投資と運転資金の2つに整理できます。
設備投資は、機械・設備の購入や工場・店舗の建設など、長い期間にわたり使う資産への投資に使われます。 返済期間は5〜10年程度と長めに設定されるのが一般的です。
運転資金は、日々の事業運営に必要な資金で、仕入れ代や人件費、家賃などの支払いに充てられます。 返済期間は比較的短く、1〜3年程度が多いです。
自社の状況や目的に合った融資の種類を選択することで、より効果的な資金調達が可能になります。
▶︎関連記事:スタートアップ企業は、日本政策金融公庫による「創業融資」を使って、良い条件で資金調達が可能です。詳しい内容はこちらの記事をご覧ください!
銀行融資のメリット・デメリット
銀行融資には他の資金調達手段と比べて、独自のメリットとデメリットがあります。資金調達を検討する際には、長所と短所をしっかりと理解したうえで、判断することが大切です。
以下の表に、銀行融資の主なメリット・デメリットをまとめました。
| 比較のポイント | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 経営権 | 株式発行と異なり、経営権を維持したまま資金調達できる | 返済義務があり、キャッシュフローに影響を与える |
| 資金使途 | まとまった金額を調達でき、事業拡大に活用しやすい | 資金使途が限定され、目的外使用は原則できない |
| 信用構築 | 返済実績を積むことで銀行との信頼関係が築ける | 審査があり、創業してすぐの企業は融資を受けにくい |
| コスト | 株式調達と比べて、調達コストが安く分かりやすい | 利息の支払いが発生し、業績にかかわらず返済が続くが悪化しても返済義務は消えない |
| 柔軟性 | 複数の金融機関で条件を比べて選べる | 担保や保証人を求められる場合がある |
注目すべきメリットは、経営権を手放さずに資金調達できる点です。VCなどから出資を受ける場合、出資に伴い株式を譲渡する場合が多く、株式が希薄化するといった問題が生じるリスクがあります。しかし銀行融資では、そうした懸念がありません。
一方で、銀行融資は、業績にかかわらず返済が計画どおりに続くことも認識しておくべきです。事業が計画通りに進まなくても、決められた返済スケジュールに従って返済する必要があります。
▶︎関連記事:銀行融資のメリット・デメリットをさらに学び、他の資金調達手段とどう使い分けるべきかを知りたい方は、こちらの記事もあわせてお読みください!
コロナ禍以降の銀行融資の現状と今後の見通し
コロナ禍を経て、銀行融資を取り巻く環境は大きく変化してきました。
ここでは、現在の融資環境と今後の見通しについて、以下の3つのポイントから解説します。
- 「ゼロゼロ融資」終了後の融資環境
- 今後の利上げが融資環境に与える影響
- 金融機関の姿勢と審査基準の変化
「ゼロゼロ融資」終了後の融資環境
コロナ禍での緊急支援策として実施された「ゼロゼロ融資」は終了し、現在は通常の審査基準に戻っています。
「ゼロゼロ融資」とは、実質的に無利子・無担保で借りられる特別な融資制度です。 利息もゼロ、担保もゼロで融資を受けられるので、「ゼロゼロ融資」と呼ばれます。
新型コロナウイルス感染症が猛威をふるった2020〜22年にかけて、多くの中小企業の資金繰りを支えました。この制度により、売上が激減した企業も資金を調達でき、事業を続けられるようになったのです。
2022年度中小企業白書(中小企業庁)には、2020年の第2四半期以降、借入金月商倍率(月商の何倍借入金があるか)が高まっている様子が紹介されています。特にサービス業や小売業での伸びが大きく、例えばサービス業では5.0倍(2020年第1四半期)から5.8倍(2021年第4四半期)へと増加しました。コロナ禍を受けて、融資を受けたことで返済余力が小さくなってきました。
しかし2021〜23年にかけて、ゼロゼロ融資は段階的に終了しました 。ゼロゼロ融資が終わり、中小企業は以下の2つの変化に直面しています。
- 審査基準の厳格化
- ゼロゼロ融資の返済が本格的に開始
まず、審査基準が厳格化され、財務状況や事業計画がより慎重にチェックされるようになりました。コロナ禍で特別に緩和されていた基準が、元の水準に戻ったと言うべきでしょう。
さらに、過去に借り入れを受けたゼロゼロ融資の返済が本格的に始まりました。据置期間(返済を猶予される期間)が終わった企業から順に返済が始まっており、返済への負担が生じています。
利上げが進むことで銀行融資に与える影響
日本の金融政策は量的・質的緩和からの転換を迎えており、今後の利上げが銀行融資に大きな影響を与える可能性があります。
金利が上昇すると企業が支払う利息が増えるため、資金繰りに影響が出ます。特に、既に多額の借り入れがあり、利益率の低い企業では、利払いが大きくなることで経営を圧迫するリスクがあります。
金利上昇は新たに融資を受ける際の審査や条件にも影響を与えます。金融機関は、金利が上昇すると返済が滞る可能性が高まると認識しています。そのため、融資先の返済能力をより慎重に審査しようとし、融資条件が厳しくなる可能性があるのです。
利上げによる環境の変化へ対応するために、あらかじめ余裕を持った資金計画を立てることが重要です。金利が低い今のうちに、将来必要になる資金を確保しておくことで、利上げ後の高金利での借り入れを避けられます。既に契約している借り入れの金利を見直し、金利の引き下げや固定金利への切り替えができれば望ましいです。
利上げが見込まれる経済においては、銀行融資以外の資金調達方法も視野に入れておくのがおすすめです。例えば、RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)を使えば、将来の売上予測に応じて資金を調達できます。銀行融資とRBFを組み合わせて活用できれば、事業をより大きく、スピーディーに成長させることも可能です。
▶︎関連記事:銀行融資についてより深く学び、RBFとどう組み合わせればよいかを知りたい方は、こちらの記事もお読みください!
金融機関の姿勢と審査基準の変化
- 「資金繰り支援」から「融資先を見極めて審査」へ移行しつつある。
- コロナ後、銀行が重視する審査項目やポイントを解説する。
- 経営者が信頼を得るために情報を開示する姿勢が求められる。
金融機関の姿勢は、資金繰りに対する支援から、融資先を見極めて審査へと移行しつつあります。
コロナ禍においては、企業の倒産を防ぐことが優先され、比較的緩やかな基準で審査がされてきました。しかし現在は、持続的に成長し収益を見込める企業かを見極める、本来の審査スタイルに戻っています。
新型コロナウイルス感染症が終わって、銀行が重視する審査ポイントとして以下のようなものがあります。
- 事業の収益性や将来性
- 財務の健全性
- 経営者の資質と経営計画の妥当性
こうした審査基準の変化に対応するには、日ごろから財務・売上データをきちんと整備し、事業計画を定期的に見直すことが大切です。金融機関との関係を構築しておくのも融資を成功させるうえで重要となります。定期的に事業報告を行うなど、コミュニケーションを密にするのがおすすめです。
▶︎関連記事:銀行が重視する審査ポイントを知りたい方は、この記事もぜひお読みください!
銀行融資に関するよくある質問(FAQ)
銀行融資を検討する際、多くの経営者が抱く疑問について答えていきましょう。
Q1. 銀行はいくらまで貸してくれますか?
中小企業白書(2022年度版)のデータを元に試算すると、月商に対する借入額は、平均して2.1倍〜4.2倍となります。借入金の月商に対する比率は業種ごとに大きく異なります。
主な業種ごとに月商の何倍借り入れがあるかを下の表にまとめました。
| 業種 | 借入金月商比率(倍) |
|---|---|
| 建設業 | 2.3 |
| 製造業 | 4.0 |
| 卸売業 | 2.1 |
| 小売業 | 2.8 |
| サービス業 | 4.2 |
注:2018年第1四半期〜2020年第1四半期における借入金月商比率を、業種ごとに平均した値を掲載。
引用:中小企業庁「中小企業白書 2022年度」の値をもとに筆者計算。
表の数値には銀行融資以外の借り入れも含まれます。自社の業種に当てはまる数値よりも、やや低い比率を融資額の目安とするとよいでしょう。
設備投資に必要な資金を借り入れる場合は、月商との比率だけではなく、事業計画の収益性もより重要な判断材料になります。設備を使って生み出される利益をもとに返済できる範囲で、融資を受けるのが基本です。
信用保証協会付き融資の場合は保証限度が設定されており、上限を超える額を借りることはできません。一般的な保証枠は無担保で8,000万円、有担保を含めると最大2億8,000万円までとなっています(2025年11月現在)。
ただし、融資を受けられる金額は企業の財務状況や事業計画、担保の有無などによって大きく異なり、一律の上限はありません。創業間もない企業や実績が少ない場合は、上で紹介した目安よりも少ない額からスタートすることも多いです。
Q2. 担保や保証人がなくても借りられる?
担保や保証人がなくても借りられる融資制度は存在します。ただし、条件や限度額に制約があることを理解しておきましょう。
例えば、信用保証協会付きの融資制度を利用すれば、担保なしで最大8,000万円までの借り入れを受けられます。この制度では、信用保証協会が債務を保証するため、個人で保証人を立てる必要は原則ありません。
日本政策金融公庫による創業融資も、原則として無担保・保証人なしで利用できる制度です。スタートアップなど特定の条件を満たせば金利の優遇も受けられ、創業間もない企業にとって有力な選択肢となります。
Q3. 銀行融資の利子はいくらですか?
銀行融資にかかる利子は、融資の種類や企業の信用力、市場環境によって変動します。おおむね年0.5%から3%程度の範囲で、金利を設定する場合が多いです。
プロパー融資の金利は、年1%から3%程度が一般的です。金利は比較的低めですが、銀行が全てのリスクを負うため、信用力が低く、創業直後の企業は利用が難しいです。
信用保証協会付き融資の場合、金利は年1.5〜3%程度とされています。ただし、金利に加えて保証料が必要となるので注意しましょう。例えば東京信用保証協会であれば、保証料は0.3〜2.2%の範囲で設定されています(一般保証の場合、2025年11月現在)。
企業の信用力による違いも大きく、財務状況が良好で返済能力が高いと評価される企業ほど、低い金利が適用されます。逆に、創業間もない企業や財務状況に不安がある企業は、高めの金利が設定される傾向があります。
融資を受ける際は、金利だけでなく、保証料や手数料なども含めた実質的なコストを確認することが大切です。
Q4. 融資の審査はどのくらいかかりますか?
融資の審査期間は、一般的に2週間から1か月程度が目安となります。
プロパー融資では、銀行のみの審査で完結するため、2週間から1か月程度で融資が実行される場合が多いです。大口融資や初めての取引の場合は、慎重な審査が行われるため、時間がかかる傾向にあります。
信用保証協会付き融資や制度融資の場合は、金融機関だけでなく保証協会による審査も必要となるため、より長い時間を要します。信用保証協会付き融資であれば1か月〜1か月半程度が目安です。制度融資であれば、自治体による審査もあり、さらに時間がかかります。
Q5. 融資に通らない理由は何ですか?
融資の審査に通らない主な理由として、
- 返済能力をはっきりと示せない
- 事業計画に不備がある
などが挙げられます。
返済能力を明確に示せないのは、融資に通らない大きな原因となります。
- 営業利益の赤字が続いている
- 過去の返済に遅延がある
- キャッシュフローが不安定である
といった状況だと、融資を受けることが難しくなります。銀行は「貸したお金が返済されるか」を重視するため、返済能力の証明が不十分だと審査は通りません。
過去の財務状況だけでなく、今後の事業計画に不備がないかも審査結果に大きく影響します。
- 資金の使いみちがはっきりしない
- 売上や利益の予測が非現実的である
- 市場や競合他社の分析が足りない
といった計画内容では、金融機関の審査は通過できません。
まとめ
銀行融資を活用するためには、基本的な仕組みや種類を理解することが重要です。 プロパー融資や保証協会付き融資など、それぞれの種類ごとに特徴をつかみましょう。成長ステージや資金の使いみちに合わせて適切な制度を選ぶことで、無理のない資金調達が可能になります。
コロナ禍を経て利上げの動きも見られるように、融資環境は刻々と変化しています。こうした状況の中で、銀行の審査基準も厳格化しています。 財務状況はもちろん、経営者の姿勢や事業計画の実現性も重要です。 日ごろから数字を整理し、信頼できる情報を金融機関に伝えられるよう準備をしておきましょう。
銀行融資だけでなく、RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンシング)を組み合わせることで、柔軟に資金調達へ向けた戦略を立てられます。事業が成長する機会を逃さず経営につなげることが可能です。
銀行融資とRBFをどう使い分けるか、どんな時にRBFを利用すればよいかなど、ご質問・ご相談はこちらから気軽にお寄せください!
参考記事
中小企業庁 「2022年度中小企業白書」
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/chusho/b1_1_2.html
一般社団法人 全国信用保証協会連合会「ご利用条件」
https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken/
東京信用保証協会「信用保証料率の体系」
https://www.cgc-tokyo.or.jp/business/guarantee_fee/system.html
※免責事項
当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。
デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。
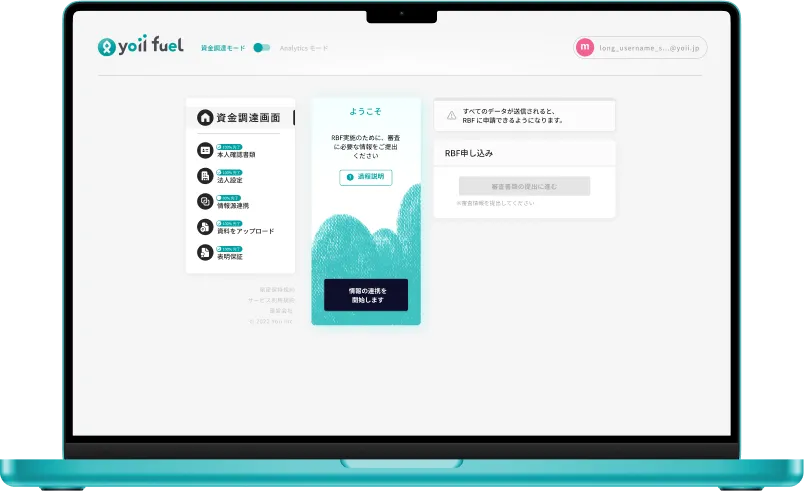
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
その他の記事
RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。