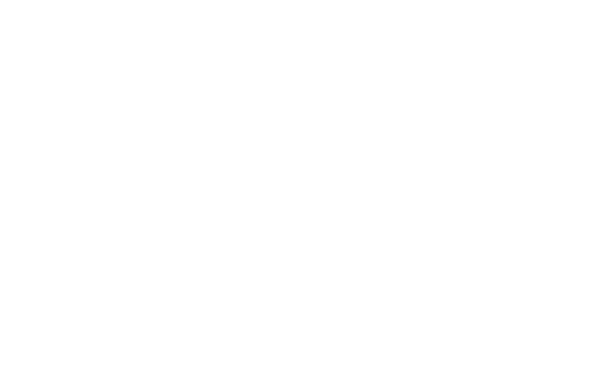2025年11月21日
円安・円高は企業経営や財務にどれだけ影響するか?(前編) 為替レートと企業財務との関係を初歩から整理する
為替変動が企業財務に与える影響とは?知っておきたい考え方
為替レートの考え方を知ろう
為替レートの変動が企業活動に影響する仕組み
為替変動の影響を受けやすい企業と受けにくい企業の違い
中小企業やスタートアップも無関係ではない理由
為替変動リスクの種類と財務への影響
外貨建て資産・負債の評価額が変動
契約と決済の為替レート差による損益が変動
為替の変動が価格競争力や生産構造にも影響
前編のまとめ
参考記事
海外からの仕入れや外国向けの販売を行う企業にとって、為替レートは売上やコスト、そしてキャッシュフローに直結する重要な情報です。
しかし、「円安・円高になると自社の利益がどれくらい変わるか」具体的な数字を把握するのに苦労されている経営者や財務担当の方も多いようです。為替レートの変動が財務にどのような影響を与えるかは、経営戦略を考える中であらかじめ検討しておく必要があります。
今回の記事では、為替レートが動くと、どのような仕組みで企業財務に影響するのかを説明します。輸入・輸出それぞれのケースで、為替変動によって利益やコストがどの程度動くのかも試算しました。
為替による影響の大きさを知り、その対策を考えるために、
- 「為替感応度」についての考え方
- 金融取引や契約条件、資金調達手段を組み合わせたリスクヘッジの方法
- レベニュー・ベースド・ファイナンシング(RBF)を活用し、為替変動による資金繰り悪化を乗り越えるための考え方
も紹介していきます。
前編となるこの記事では、為替レートの基本的な考え方や、為替が変動することで企業財務にどのような影響が生じるかを、一から整理していきましょう。
為替変動が企業財務に与える影響とは?知っておきたい考え方
為替レートの変動は、企業の売上や原価、そしてキャッシュフローに効いてくる重要な外部要因です。この記事ではまず、為替レートが「どのような仕組みで企業活動に影響するのか」を基礎から押さえましょう。
為替変動の影響を受けやすい企業と受けにくい企業の違いを整理します。基本を知ることで、中小企業やスタートアップこそ、為替レートの影響を考えておくべき理由も見えてくるでしょう。
為替レートの考え方を知ろう
為替レートは、日本と海外のお金の交換レートを表します。通貨の「値札」にあたると思えばよいでしょう。
例えば、海外の企業が取り扱う生成AIサービスを使うために、月20ドルの個人プランを契約するとします。日本にいる私たちが月額の代金を支払うためには、20ドルを準備しなくてはなりません。しかしもちろん、日本の生活ではドルを使っておらず、手元にあるのは日本円だけです。
そこで、日本円をドルに交換する取引が必要になります。こうした取引をするのが外国為替市場と呼ばれる場所です。 市場では、「1ドル=150円」という形で値札がついています。これは「1ドルを手に入れるには、150円を支払えば交換できる」ことを意味します。この値札を為替レートと呼んでいるのです。
生成AIサービスの価格が月20ドルですから、日本にいる私たちは、
- 契約プランの価格は20ドル
- 為替レートは1ドル=150円、1ドルを手に入れるのに150円が必要
という状況です。つまり、20(ドル)×150(1ドルあたり必要な円)=3,000円の日本円があれば、1ヶ月の契約ができますね。

さて、通貨の値札である為替レートの値が変動すると、海外と取引を行う企業の仕入れ価格や収益も変わります。
先ほどの生成AIサービスの例をもう一度見てみましょう。もし為替レートが「1ドル=150円」から「1ドル=155円」に変わったら何が起きるでしょうか。このときは
- 契約プランの価格は20ドル
- 為替レートは1ドル=155
150円
と状況が変わり、20×155=3,100円の日本円が必要です。先ほどより100円余計に円を支払うことになってしまいました。ドル建て価格(ドルで表記された価格)は変わっていないのに、日本円の支払額で見ると3.3%の値上がりとなります。
「1ドル=150円」から「1ドル=155円」のように為替レートが変化することを、円安(ドル高)と呼びます。
海外からの商品を外国通貨建ての価格で購入する場合、円安が進むほど、同じ数量でも支払額が増える仕組みになります。上の例でも見たとおり円安になると、ドルを入手するために、より多くの円を支払う必要が生じるためです。
ちなみに、「1ドル=150円」から「1ドル=145円」のように、為替レートが動く現象を円高(ドル安)と呼びます。 円高になると円の価値が上がり、同じ金額の外貨をより少ない日本円で支払うことが可能です。
実際、1ドル150円から145円になると、上で見た生成AIサービスの例では支払額が100円少なくなります。これは約3.3%の値下げと同じ効果です。
為替レートの変動が企業活動に影響する仕組み
ここまでで説明してきた為替レートの影響は、海外との取引がある企業でも同じように生じます。
仕入れなどで、海外からの商品を海外通貨で購入する(例えばドルで支払う必要がある)場合を考えましょう。この場合、支払いのために準備する日本円は為替レートによって変わります。円安が進めば進むほど、同じ取引数量でも、円で見た支払額が増えてしまいます。逆に円高になると、円の価値が上がり、同じ取引内容でも、より少ない日本円で代金を支払うことが可能です。
海外に向けて輸出を行う企業であれば、円安は売上額を押し上げる効果を持ちます。円に換算した後の売上額が増えることで、財務上の利益も拡大しやすくなります。一方で円高が進むと、外貨で得た収益を円に直した金額は小さくなるため、売上が減ってしまうのです。
ここまで説明した、円安・円高が企業の取引に与える影響は下の表のように整理できます。
| 円安になると... | 円高になると... | |
|---|---|---|
| 輸出 (海外での製品販売) | 日本円で見ると売上増・収益増 | 日本円で見ると売上減・収益減 |
| 輸入 (海外から仕入れ・購入) | 日本円で見るとコスト増・収益減 | 日本円で見るとコスト減・収益増 |
為替の影響は財務諸表上の数字にとどまりません。契約を結んだ後に、決済時における為替レートが変動すると、キャッシュフローも変わることに注意が必要です。実質的な仕入れ価格が上がれば、販売価格の見直しや利益率の調整も必要になります。結果的に企業の競争力や事業戦略へと影響が及んでいくでしょう。
為替レートの変動は、モノを輸出・輸入している企業だけが影響を受けるわけではありません。海外サービスを利用したり、外貨建てのサブスク契約を持つ企業にも影響します(上で紹介した、生成AIサービスの代金を支払う例を思い出してください)。
自社において、為替の影響を受ける活動を把握することが、実務での為替リスク管理の第一歩になります。
為替変動の影響を受けやすい企業と受けにくい企業の違い
為替レートの変動によって影響をどれほど受けるかは、企業によって大きく変わります。
次のような特徴を持つ企業は、為替による影響を受けやすいと考えられます。
- 輸出・輸入に大きく依存している
- 外貨建て価格の取引が多い
- 為替の影響を価格に転嫁させづらい
まず為替の影響を受けやすいのは、輸出・輸入比率が高い企業です。輸入に依存している企業は、円安で仕入れコストが上がってしまいます。海外のサービスをよく用いる企業も、同じ傾向が見られます。輸出中心の企業は、円安になると日本円で見た売上が増える構造です。
海外との取引が多い企業の中でも、外貨建て取引の比率が高いほど、為替レートの影響をさらに受けやすくなります。
原材料などの値上げを、価格に転嫁しやすいかどうかも重要なポイントです。価格競争の激しい業界を考えてみましょう。こうした業界では、仕入れコストの上昇を販売価格にあまり転嫁できません。したがって、為替変動の影響がそのまま利益の減少につながります。
一方で、独自性のある製品・サービスを持つ企業、もしくは契約を通じて価格を調整しやすい企業は、為替レートが変わっても、値上げ・値下げを通じて影響を吸収しやすい環境にあります。
業種ごとに違いを見ると、製造業や卸売業は輸出に関わる企業の割合が多く、為替の変化に敏感です。 例えば、海外サプライヤーに依存せざるを得ない製造業者であれば、想定以上の円安が起こると、原価が急上昇するダメージを強く受けることになります。
国内で取引が完結している企業であれば、為替変動のリスクを直接受けるおそれはあまりないでしょう。 国内での調達比率が高い企業や、契約上の価格を円建てにしている企業では、為替の影響を受けにくい構造がつくれます。
中小企業やスタートアップも無関係ではない理由
為替レートの変動により事業が影響を受けるのは、大企業だけの問題と見る人もいるようです。しかし実際には、中小企業やスタートアップにも大きな影響が生じ得ます。
仕入れを海外との取引に頼る企業では、円安になるほど支払額が増え、利益率が急激に圧迫されます。大企業よりも小規模な企業ほど、資金繰りの余裕を失いやすく、リスクに脆弱となりがちです。有名なクラウドサービスの多くは外貨建て価格で請求されるため、さまざまな業種で為替レートの影響を受けやすくなっている点も見逃せません。
大企業と比べると、中小企業は価格転嫁も難しい傾向にあります。 競合が多く、値上げをしにくい市場構造であるほど、仕入れコストの上昇を吸収できません。円安によって突然、支払いが増えることで、運転資金に余裕がない企業ほどキャッシュフローの悪化が大きな負担となります。
サブスクリプションサービスや越境ECなど、海外向けにサービスを提供する日本企業も為替レートの影響を受けます。円高が進むと、日本円で見た売上が減ってしまうため、やはり為替によるリスクからは逃れられません。
▶関連記事:大企業と比べて中小企業は、コスト上昇を値上げでカバーするのが難しいことが調査でも明らかにされています。価格転嫁の実態にご関心がある方は「インフレで増える生産コストを値上げでカバーできるか?」もお読みください!
為替変動リスクの種類と財務への影響
為替変動のリスクは、企業の財務にさまざまな形で表れます。
ここでは、為替レートが変わることによる影響を、以下の3つに整理して紹介しましょう。
- 外貨建ての資産や負債の評価額が変わる
- 契約を締結・決済するときの為替レートの差で損益が生まれる
- 為替の変化が、価格競争力や製造プロセスにも影響する
外貨建て資産・負債の評価額が変動
外貨建ての資産や負債を保有している企業では、為替レートが変動すると評価額が自動的に変わります。
例えば、1万ドルの売掛金がある場合を考えます。円安が進むほど、円に換算した資産額が増えます。逆に、円高になると売掛金の価値が目減りし、帳簿上の評価損が発生してしまいます。
同じように、外貨建てでの買掛金や借入を抱える企業では、円安になるほど負債額が増え、円高になれば実質的な負担が軽くなる仕組みです。
短い期間で為替レートが大きく変わった場合に、評価損益も激しく動きやすい点に注意しましょう。輸入比率が高い企業は、円安局面になると円建ての負債が膨らみ、利益が圧迫されやすいです。
逆に、輸出企業は円安が進むと資産の評価額が増えることになります。しかし、それが実際の入金まで維持されるとは限りません。原則として、あくまで決済時の為替レートで評価額が確定します。
契約と決済の為替レート差による損益が変動
外貨建て価格で取引すると、契約を結んだ当時と実際に決済する時点で、為替レートが異なることもよくあります。為替レートにこうした差が生じると、「為替差益」や「為替差損」という形で企業の利益が増減します。
例えば、海外の企業と1万ドルの仕入れ契約を結んだとします。想定レートが1ドル=150円だった場合、もとの支払い想定額は150万円です。しかし、決済時に円安が進み1ドル=155円になれば、支払い総額は155万円に増え、結果として5万円の為替差損が発生します。
一方で、決済時に円高が進んでいれば支払額は減り、為替差益を得られます。
為替差損(益)は、実際に決済されるタイミングで財務に影響する点が特徴です。特に、契約から決済までの期間が長い事業を営む場合は注意が必要です。契約後の数週間〜数か月の為替変動で負担が大きく変わり、資金繰りに直結するリスクになりかねません。
理論上は、為替レートがどこまで動くかに制限はありません。予定していた利益の大きさが簡単に変わってしまうリスクもあります。
為替の変動が価格競争力や生産構造にも影響
長い目で見ると、為替レートが変われば、企業の価格競争力や生産体制そのものにも波及します。
輸出企業にとっては、円安は有利に働きます。海外市場で同じ外貨建て価格を設定しても、円に換算した収益が増え、利益が拡大しやすくなります。したがって、円安が進むと、現地の製品価格を安く提示することも可能です。その結果、海外の競合他社に対する価格競争力が高まります。この優位性こそが、「円安は輸出企業にとって有利である」と言われる理由です。
海外から商品やサービスを購入している企業では、逆の影響が生じ得ます。円安が進むと仕入れ原価は大きくなり、販売価格が変わらない限り利益率も下がります。競争が激しい市場では価格転嫁も難しいです。こうした状況が続くと、生産拠点を海外へ移したり、さまざまな国で調達先を探したりするなど、生産構造を見直す動きにつながります。
前編のまとめ
前編となるこの記事では、為替レートの基本的な考え方と、為替変動が企業経営・財務にどのような形で影響を及ぼすかを見てきました。
次の後編では、ここまで解説した考え方をもとに、円安や円高によって企業が受ける影響を試算しましょう。簡単なシミュレーションを通じて、中小企業やスタートアップでも無視できない効果があると分かります。為替変動の影響を少しでも和らげる方法についても議論します。
参考記事
馬塚元希・島谷薫乃(2022) 「企業の為替感応度と為替ヘッジ」、財務省『ファイナンス』
経済産業省 『通商白書2024年度版』
※免責事項
当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含むことがあります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。
デットでもエクイティでもない新たな資金調達手段でSaaS企業を支援
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。
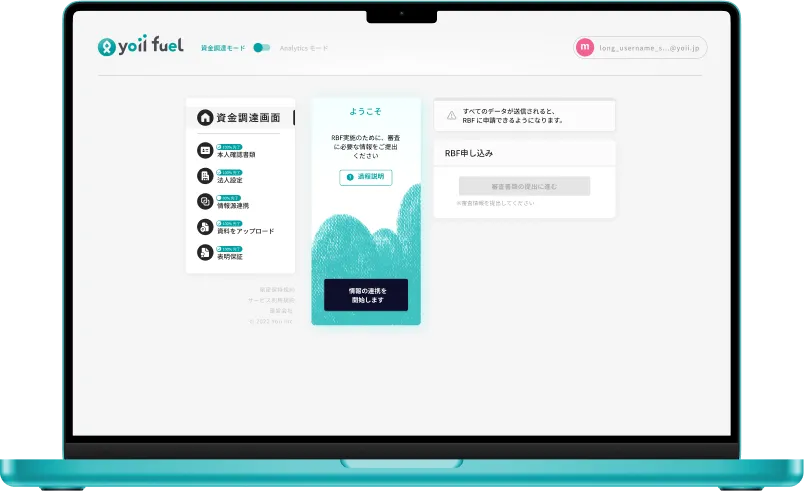
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
その他の記事
RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。